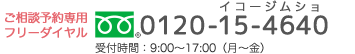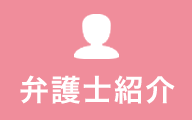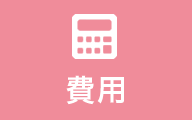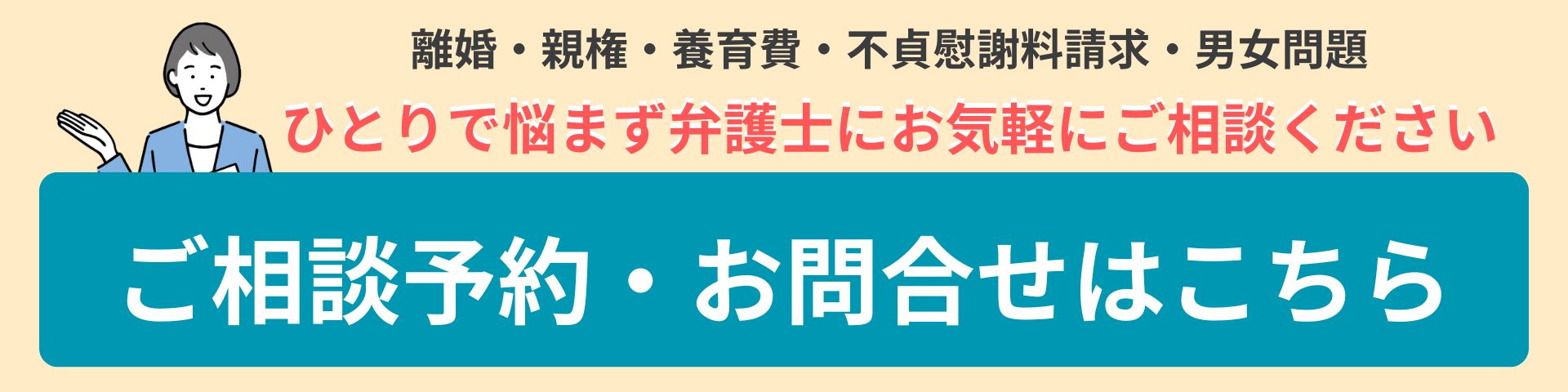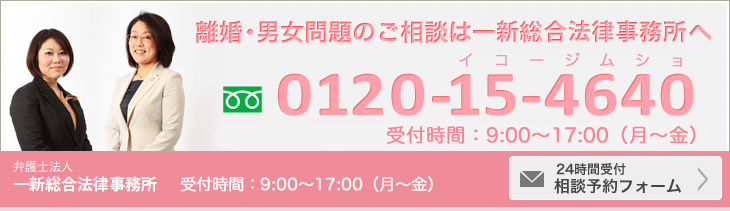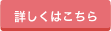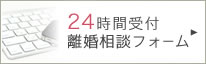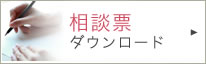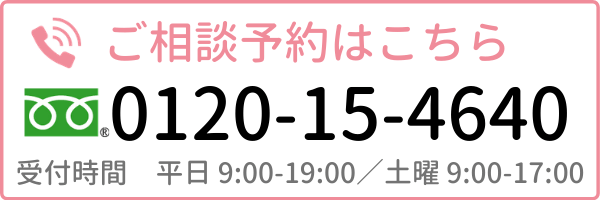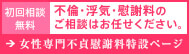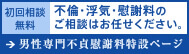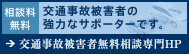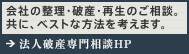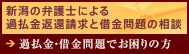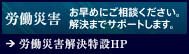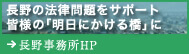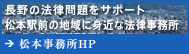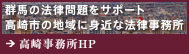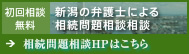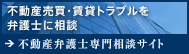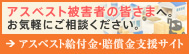モラハラ夫・妻と離婚したい!モラハラの特徴と必要な準備
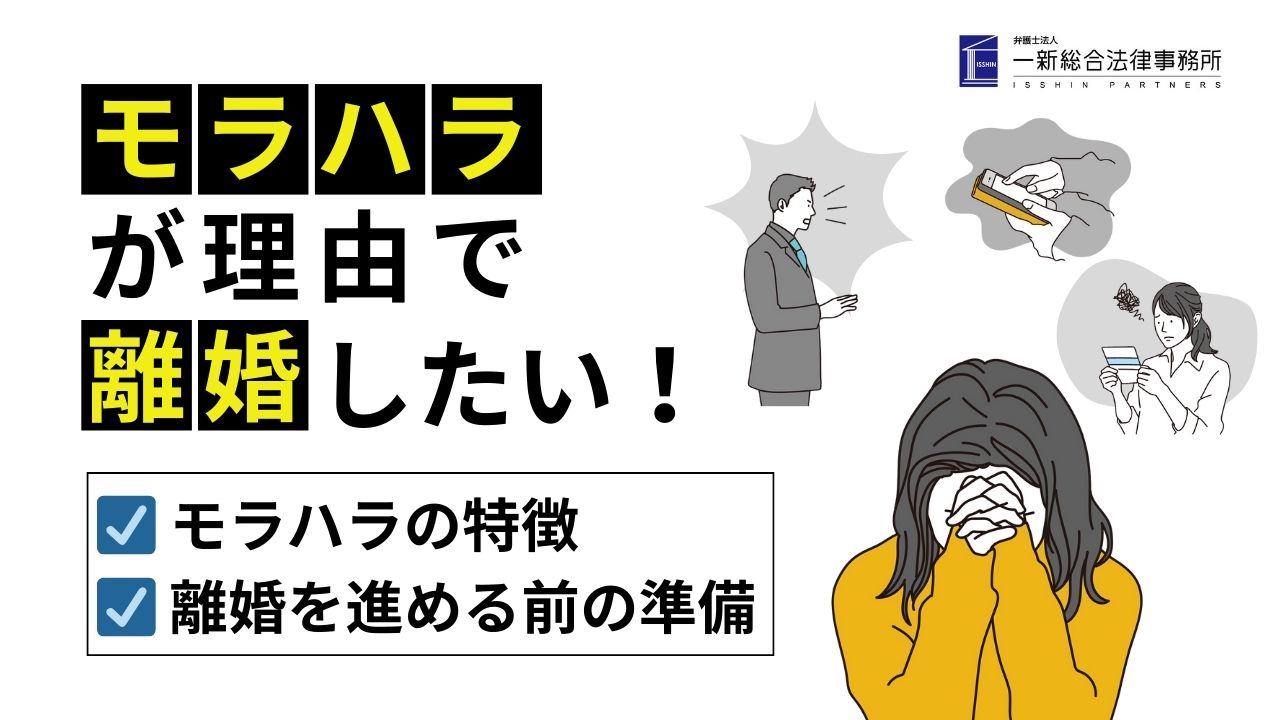
(最終更新日:2025年8月18日)
精神的な暴力ともいわれるモラハラは、物理的な暴力を振るうわけではないのですが、言葉や行動、態度によって相手に精神的苦痛を与えます。
直接的な身体的暴力よりも表面化しにくいため、被害者の苦痛が見過ごされがちです。
夫(もしくは妻)からのモラハラを理由に離婚を考える際には、まずあなたが受けている被害がモラハラに当たるのかどうかについて正しく理解することが大切です。
本記事では、モラハラをする人の特徴をはじめ、モラハラの具体例、モラハラが原因で離婚する場合の準備や手段、実際の手続きに関するポイントを解説していきます。
1. モラハラ(モラルハラスメント)とは?
モラルハラスメントとは、直接的な暴力ではなく、言葉や態度によって相手を追いつめる精神的虐待・精神的暴力を言います。
内閣府男女共同参画局では、モラハラをDVの一種として「精神的DV」と分類されることもありますが、法的には身体的DVと比較して立証や評価に難しさがあるのが現実です。
最近では、モラルハラスメントを行う夫(妻)のことを、略してモラハラ夫・モラハラ妻と呼んだりします。
【参考】内閣府男女共同参画局「ドメスティック・バイオレンスとは」
2. モラハラ夫(妻)の特徴
次に、モラハラを行う配偶者にみられる特徴についてです。
| ・自己顕示欲が強い ・自分の非を認めない ・突然怒り出すことがある ・嫉妬心が強い ・対外的には人あたりがよい |
自己顕示欲が強い
自分は特別で優秀あるという感覚を有し、他者から認められることへの強い期待を持っています。
プライドが高く、「仕事ができる」「才能がある」「優秀である」と見られたいと強く思っており、また、自分は、そのような賛辞を受けるにふさわしいと考えています。
これは、客観的にそのような立場にあるか否かとは無関係です。 周りから自分がどう見られているかをとても気にする人が多いのも特徴です。
また、家庭はこうあるべき、妻(夫)はこうあるべきといった自分の価値観にとらわれている方が多いといえます。
自分の非を認めない
自分が浮気をしたとしても「浮気させるようなお前が悪い」というように、自分の非を認めないプライドの高さも特徴です。
また、共感性に欠け、相手の気持ちを理解することができない傾向があります。
周囲から間違いを指摘されても、相手の意見を聞く耳をもたず、相手に対して徹底的に反論しやりこめようとします。
突然怒りだすことがある
些細なことで突然怒ることがあることも、モラハラ夫(妻)の特徴です。
そうすることで、相手を不安な状態に置き、自分の顔色をうかがわせるようにします。
定期的に怒ることで、夫婦関係に上下関係を作りだし、常に相手を自分に従わせるようにしたいのです。
その際、相手に劣等感を植え付けるような言動で、常に自分の意見が正しいと思わせようとする傾向があります。
嫉妬心が強い
嫉妬心が強いのもモラハラ夫(妻)の特徴の1つです。
また、他人が自分に嫉妬していると思い込むケースも多く見受けられます。
被害者は、相手からの嫉妬を恐れ、外部の人間と接触しなくなり、結果的に、問題が家庭内に閉じ込められてしまうのです。
その際、相手に劣等感を植え付けるような言動で、常に自分の意見が正しいと思わせようとする傾向があります。
3. 被害者が陥りやすい心理
モラハラの被害に遭いやすい人は、以下のような傾向があります。
| ・真面目で我慢強い ・他者への思いやりが強い ・自己評価が低い ・責任感が強く失敗を避けたがる |
相手の言動に反論せず、加害者の言葉を鵜呑みにして「自分が悪かったのかも…。」と相手の言い分を受け止めてしまいがちです。
こうした素直さは本来美点ですが、モラハラ被害では逆手に取られ相手の態度をよりエスカレートさせる恐れがあります。
こうした心理を自覚することで、早い段階で「これはおかしい」と気付ける可能性が高まります。
4. モラハラに該当する?チェックリスト
内閣府男女共同参画局のサイトでは、精神的なDVに該当する行為として以下のものがあげられています。
• 大声でどなる
• 「誰のおかげで生活できるんだ」「かいしょうなし」などと言う
• 実家や友人とつきあうのを制限したり、電話や手紙を細かくチェックしたりする
• 何を言っても無視して口をきかない
• 人の前でバカにしたり、命令するような口調でものを言ったりする
• 大切にしているものをこわしたり、捨てたりする
• 生活費を渡さない※
• 外で働くなと言ったり、仕事を辞めさせたりする※
• 子どもに危害を加えるといっておどす
• なぐるそぶりや、物をなげつけるふりをして、おどかす
_________
※生活費を渡さない、もしくは仕事を制限するといった行為は、「経済的なもの」と分類される場合もあります。
【参照】内閣府男女共同参画局「ドメスティック・バイオレンスとは」
これらの言動に当てはまるものがないかチェックリストを作成し、確認することで、あなた自身の被害を客観的に把握しやすくなります。
5. モラハラを理由に離婚できる?
配偶者からのモラハラを理由に離婚したい場合、相手の行為が「婚姻を継続しがたい重大な事由」と判断されれば離婚することができます。
ただし、モラハラ被害を客観的に立証できるための証拠が必要となります。
証拠集めの過程で相手に悟られてしまうと、証拠を隠されたり、さらに攻撃を受けたりするリスクがあります。
必要であれば弁護士などの専門家に相談しながら、慎重かつ計画的に進めるよう注意しましょう。
モラハラを立証するための証拠収集
モラハラを理由に離婚を円滑に進めるためには、客観的な証拠が必要となります。
具体的には以下のようなものが挙げられます。
| 【モラハラ被害を立証するために有効な証拠】 ①モラハラを受けているときの録画・録音データ ②メール、SNS、LINEなどのメッセージ ③モラハラ被害について詳細に記録をした日記やメモ ④精神科・心療内科での意思の診断書や通院履歴 ⑤警察や弁護士、専門機関への相談履歴 |
①モラハラを受けているときの録画・録音データ
実際に被害を受けている証拠として録画、録音は有効です。
一方で、被害を記録していることが相手にばれてしまうと、より一層深刻な被害を受ける可能性がありますので慎重に行動する必要があります。
②メール、SNS、LINEなどのメッセージ
相手から送られてきたメールなどは保存しやすく、証拠としても有効です。
削除されることがないように、保存した記録は複数のデバイスで保管するなどの対策をするとよいでしょう。
③モラハラ被害について詳細に記録をした日記やメモ
モラハラに該当する精神的な暴言や脅迫があった際には、日付や時間、内容を正確に記録しておくことで、後から被害を立証しやすくなります。
できるだけ詳しく記録を残しましょう。
④精神科・心療内科の診断書や通院履歴
モラハラ被害により通院をしている場合には、医師による診断書なども用意すると効果的です。
また、警察や弁護士、専門機関(配偶者暴力相談センター、女性センター※例:新潟県女性財団など)への相談歴があると、客観的に被害の深刻度が立証されやすくなります。
別居のタイミングと生活資金の確保
モラハラ被害を受けているなかで離婚を切り出した場合、同居のままでは被害がより深刻になるリスクがあります。
とても勇気がいる決断ですが、安全を確保しながら生活の基盤を整えることで、精神的な安定を得やすくなります。
別居には賃貸物件の契約金や生活費などの資金が必要となるケースがあります。
仕事の確保や生活費の試算など、貯蓄を進めるなど、早めに準備をしておくことが不可欠です。
別居先を検討する際には、安全面や費用面の負担を考慮し、別居のタイミングや手段は弁護士と事前によく相談して決めることをおすすめします。
第三者への相談(弁護士・支援機関)
モラハラを理由とする離婚は感情の対立が激しくなりやすいため、一人で抱え込まず早期に専門家へ相談することが大切です。
法律の専門家である弁護士はもちろん、公的機関の相談窓口なども有効です。
迅速な行動は、加害者に対抗するだけでなく、自分や子供の心身を守るうえでも大きな意味を持ちます。
一人で抱え込まず気軽に相談に赴くことが離婚の長期化を阻むポイントです。
離婚問題に詳しい弁護士であれば、証拠の収集・整理や離婚後の生活設計に関するアドバイスも行うことができます。
弁護士費用が気になる方は、まずは法律無料相談や法テラスなどの支援制度を活用することも考えてみましょう。
これから離婚を切り出したいと考えている方は、以下のコラムで離婚原因別の注意点などを詳しく解説しています。
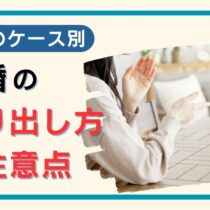
6. 離婚までの流れ
離婚に至るまでには協議、調停、裁判などの手段がありますが、それぞれメリット・デメリットが存在します。
協議離婚(話し合い)
協議離婚は、夫婦間の話合いで合意ができれば離婚が成立する方法です。
合意がスムーズに得られれば、比較的短期間で離婚が成立し、その後の生活再建にも早く取り組めます。
ただし、モラハラ夫(妻)がそもそも話し合いの姿勢を見せない場合や、被害者が精神的に対等に交渉できない環境では、協議離婚の実現は困難かもしれません。
加害者からさらなる言葉の攻撃を受けたり、条件を一方的に押し付けられたりするリスクもあります。
閉鎖された空間での話し合いは避け、場所やタイミングには十分気をつけましょう。
調停離婚
夫婦の話し合い(協議)で離婚に合意できなかった場合には、離婚調停に進みます。
モラハラ被害にあっている場合は、協議をせずに調停からスタートさせることも検討しましょう。
離婚調停は、家庭裁判所に対して申し立てを行い、調停委員が間に入って話し合いを進める制度です。
当事者同士が別室で話を聞いてもらうこともできるため、対面のストレスを避けられる利点があります。
調停ではモラハラの事実を正確に調停委員に伝えるために、有効な証拠の準備と、自分の主張をいかに明確に示せるかが重要になります。
調停の前に、離婚問題に注力する弁護士に相談し、どのように主張していくか検討することをおすすめします。
離婚裁判
調停で話がまとまらなかった場合、あるいは相手が協議や調停に応じない場合には、最終的に裁判での離婚を目指すことになります。
裁判では証拠の有無が結果を左右し、長期間にわたる可能性があります。
裁判離婚の場合、法律に定められている離婚事由がなければ離婚は認められません。
モラハラを理由に離婚を求める場合、民法770条1項5号の『その他婚姻を継続し難い重大な事由』に該当する必要があります。
あなたのケースがこの要件に該当するかどうかは、証拠や婚姻関係全体の状況により個別に判断されます。
裁判ともなれば精神的にも負担が大きくなるため、弁護士のサポートを受け、法的に有効な証拠を整理し、早期解決に向けた戦略を立てることが重要となります。
離婚成立までの流れは以下のコラムで詳しく解説しています。
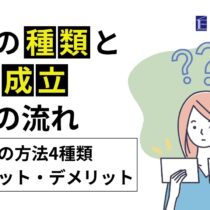
7. モラハラが離婚原因の場合、慰謝料はもらえる?
離婚の慰謝料請求が認められるためには、法的に有効な証拠を提示して、モラハラの内容や被害の程度を証明しなければなりません。
また、請求が認められた場合の慰謝料の相場は50万~300万円程度といわれていますが、実際にはモラハラの内容や被害の回数、期間、被害者の受けた苦痛の程度(精神疾患等の診断書)、被害者の落ち度、資産状況、婚姻期間の長さや子どもの有無など、個別の事情により金額が大きく変動します。
子どもがいる場合には、金銭的な問題が離婚後の子どもの生活を左右するため、有利に離婚が進められるよう慎重に準備をしていく必要があります。
離婚の慰謝料請求の手続などについては以下のコラムで詳しく解説しています。
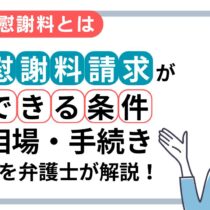
8. 子どもへの影響と親権問題
家庭内の不穏な空気や言葉の暴力は、子どもの精神にも大きな影響を及ぼすとされています。
子どもが過度にストレスを受けてしまうと、不安定な行動を起こすようになったり、日常生活に支障をきたす場合もあります。
離婚を検討する際も、親として、子どもの安全と健康を最優先にして行動しましょう。
親権・監護権をめぐる取り決めのポイント
離婚時には、どちらが親権を持つか、あるいはどのように監護権を分担するかが大きな争点となります。
モラハラを理由に離婚をする場合、子どもへの悪影響を避けるために、被害者側の親が単独で親権者となるケースも多いです。
とはいえ、子ども本人の意思も尊重される場合が多いので、無理に一方的な決め方を押し付けず、弁護士のサポートを受けながら話し合いを進めるのが円満な解決につながりやすいといえます。
9. モラルハラスメントを理由に離婚を検討される方へ
モラルハラスメントの被害者の多くは「私が間違っている」「私が悪い」と思って我慢しています。
まずは自分が被害者だということに気づくことが重要です。
初期の段階では自分が被害を受けていることに気づかず、違和感を抱えたまま日常を過ごしてしまう方も多いですが、心身に負担が蓄積していくことに変わりはありません。
モラハラ夫(妻)と離婚するためには、「離婚したい」という意思を強く持つことがとても重要です。
あなたの辛い気持ちに寄り添い、モラハラ被害への対処法についてアドバイスを行い、新しい人生がスタートできるよう弁護士がサポートいたします。
弁護士に相談するメリット
弁護士に相談することで、法律的な手続きに関する不安や、相手との交渉といった精神的な負担が大きく軽減されます。
あなたのモラハラ被害について立証するだけでなく、婚姻費用、財産分与、慰謝料、親権、養育費、面会交流などの離婚条件についてもあなたに代わって相手と交渉することができます。
調停や裁判になった場合には、裁判所への書類作成や手続きもワンストップで行うことができます。
単に離婚を成立させるだけでなく、離婚後の人生設計まで見据えた総合的なサポートが期待できます。
弁護士を選ぶときは、離婚問題やDV・モラハラ案件を多数扱っている実績があるかを確認すると安心です。
話を丁寧に聞いてくれるかどうかも重要なポイントです。
弁護士法人一新総合法律事務所には、離婚問題に注力する離婚チーム弁護士がいます。
チーム内にはメンタルケア心理士の資格を持つ弁護士も在籍しています。
離婚に関するご相談は初回45分5,000円、不貞慰謝料請求に関するご相談は初回無料相談を実施しています。
一人で悩まずに、また、「私が悪いのだから…」と思い込まずに、まずは弁護士にご相談ください。
予約受付はフリーダイヤル0120-15-4640または、相談予約フォームよりお申し込みください。
【ご注意】
◆本記事の内容は執筆日時点の法令等に基づいており、最新の法改正や裁判例等を反映していない可能性があります。最新情報については、必ず弁護士等の専門家に確認してください。
◆当事務所は、本サイト上で提供している情報に関していかなる保証もするものではありません。本サイトの利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当事務所は一切の責任を負いません。
◆本サイト上に記載されている情報やURLは予告なしに変更、削除することがあります。情報の変更および削除によって何らかの損害が発生したとしても、当事務所は一切責任を負いません。