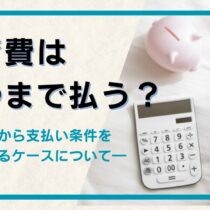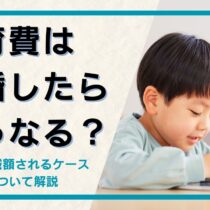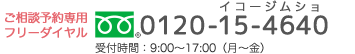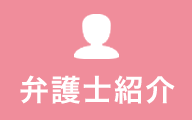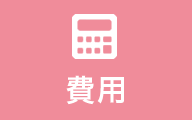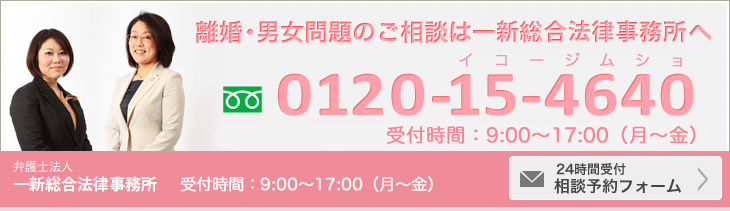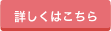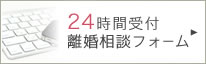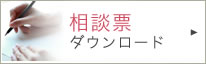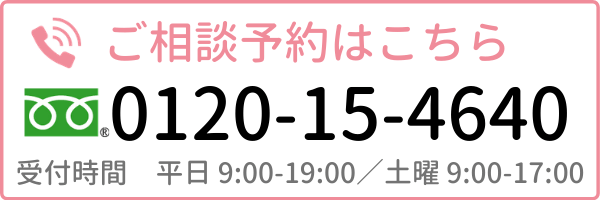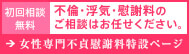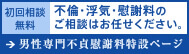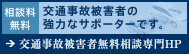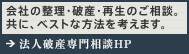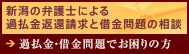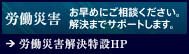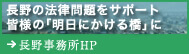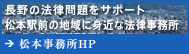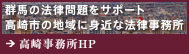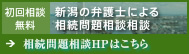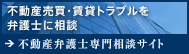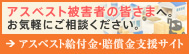養育費について
離婚後の養育費について不安を感じる方は多いのでないでしょうか。
当事務所にも、「養育費はいくらぐらいもらえるのか」「約束していた養育費が支払われなくなった」といった相談が数多く寄せられます。
ここでは「養育費とはなにか」「養育費はいつまでもらえるのか」「養育費の金額の決め方」「養育費が支払われなくなった場合の対応と予防策」などについて解説します。
1.養育費とは

養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用です。
一般的にいえば、未成熟子(経済的・社会的に自立していない子)が自立するまで要する費用で、衣食住の経費や教育費、医療費、娯楽費など、自立するまでに必要となるすべての費用をまとめて養育費と呼んでいます。
婚姻中は、子どもの生活に要する費用は、婚姻費用という形で夫婦が共同して負担しています(離婚までは、婚姻費用の中に養育費が含まれる形となります。)が、離婚後は、監護親(子どもと一緒に暮らす親)に子どもの生活費の負担が偏ってしまうことから、その公平な分担という観点から養育費の請求権が認められています。
条文上は、
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
[民法766条1項]
前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
[民法766条2項]
と定められており、ここでいう「子の監護に要する費用」が養育費です。
2.養育費はいつまで?支払い期間について
支払期間は事情により異なるが、20歳までとされる傾向
養育費をいつまで支払うか(養育費支払いの終期)については、先に述べたとおり、「子どもが経済的・社会的に自立自立するまで」ということになります。
20歳になる月までとする場合、高校卒業まで(18歳)とする場合、大学卒業まで(22歳)とする場合など様々です。
協議や調停で決める場合には、各家庭の状況に応じて柔軟に決めることができますが、協議が整わず、裁判や家事審判になった場合には、20歳になる月までとされる傾向があります。
また、財産分与や慰謝料は一括で支払う場合も多いのですが、養育費は毎月5万円といったように定期的に支払っていくのが通常です。
成人年齢の引き下げにより、養育費の支払い期間は短くなる?
令和4年(2022年)4月1日から「民法の一部を改正する法律」の施行され、成年年齢が18歳に引き下げられました。
ですが、これにより養育費の支払期間が、18歳までとなるわけではありません。
施行前に『養育費の支払いは成年に達するまで』という取り決めをしていた場合は、従前どおり子どもが20歳になるまでは、養育費は支払われることになります。
3.養育費はいくら?金額の決め方
養育費の額は、子どもの人数・年齢や双方の収入等によって決まります。
具体的な額については、養育費算定表と呼ばれる早見表が活用されており、裁判や家事審判になった場合には、この算定表の基準に沿って金額が算出されるのが通常です。
もっとも、算定表はあくまでも基準であり、特別な医療費を要する場合や、私学に通っていて高額の教育費を要する場合など、特別の事情があれば算定表の範囲外の金額が認定されることもあります。
一方で、協議や調停で養育費の額を取り決める場合には、算定表にとらわれることなく、当事者の合意さえあれば自由な金額を決めることが可能です。
養育費の金額についてもっと詳しく知りたい方は…
養育費はいくらもらえる?養育費の相場・算定方法について
4.養育費の金額はあとから変更できる?
養育費の額を取り決めたあとに、失業などで収入の大幅な変動があり、当初の取り決めどおり養育費を支払い続けることが難しくなった場合には、養育費を支払う側の当事者は受け取る側の当事者に対し、養育費の減額を求めることができます。
逆に、収入の変動により、当初取り決めた金額では子どもを養っていくことができなくなったようなときには、受け取る側が支払う側に対し金額の増額を求めることができることがあります。
養育費の金額変更についてもっと詳しく知りたい方は…
養育費を払わないとどうなる?支払いが難しいときの減額方法
5.約束どおりに養育費を払ってもらえない場合は?
相手が養育費を支払わない場合の対処方法については、養育費がどのような方法で取り決められているかによって変わってきます。
①家庭裁判所の履行勧告
養育費が調停や家事審判、裁判などで取り決められた場合であれば、家庭裁判所の履行勧告の制度を利用できます。
これは、当事者の申立てにより、家庭裁判所が養育費を支払わない当事者に対し、取り決め内容のとおり養育費を支払うよう勧告してくれる制度です。
この制度には、手数料がかからず、簡易に申立てができるというメリットがありますが、強制力がないというデメリットがあります。
②強制執行
家庭裁判所から履行勧告を行っても、養育費の支払いがなされない、またはなされる見込みがないような場合には、強制執行の方法を検討することになります。
強制執行は、家庭裁判所の調停調書、審判調書、判決書にもとづいて裁判所に申立てを行い、相手方の財産(預貯金、給与など)を差し押さえて強制的に養育費を回収する方法です。
養育費が当事者の協議で取り決められた場合でも、強制執行認諾文言付きの公正証書が作成されていれば、相手が約束を守らなかった場合に、強制執行の方法をとることができます。
しかし、口頭で約束したに過ぎない場合や、書面化されていてもそれが上記の公正証書でない場合には、直ちに強制執行の方法をとることができないので注意が必要です。
相手方の養育費の支払いについて少しでも不安がある場合には、合意を公正証書化しておくか、調停・審判などの裁判所の手続を利用することが大切といえるでしょう。
養育費不払いについてもっと詳しく知りたい方は…
強制執行とは 流れと手続き
養育費が支払われない!公正証書の作成を
6.適正な額の養育費を確実に受け取るために
養育費は、子どもが自立するまでの間、すこやかに育つために不可欠なものです。
適正な額の養育費を取り決める、養育費を確実に受け取るためにも、弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人一新総合法律事務所では離婚チーム所属の弁護士が離婚のお悩みに対応いたします。
新潟県内5拠点(新潟市・長岡市・上越市・燕三条・新発田市)と長野県(長野市・松本市)、高崎市で離婚についてお悩みの方はぜひお近くの一新総合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
▼養育費についての関連コラム▼