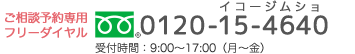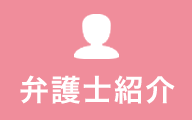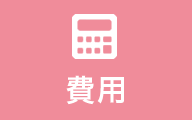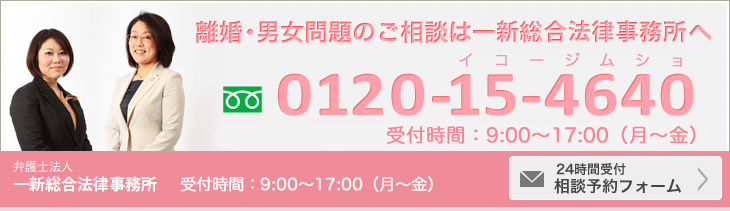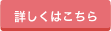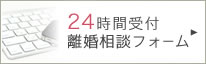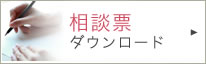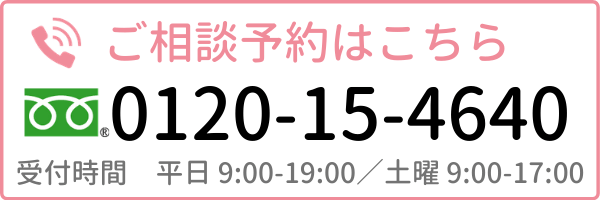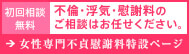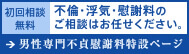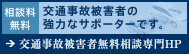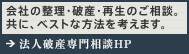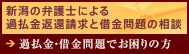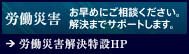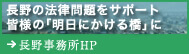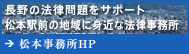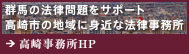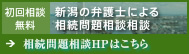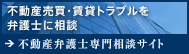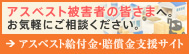財産分与について
夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際または離婚後に分けることを財産分与といいます。
離婚をすると、夫婦は別々に暮らすことになるので、婚姻期間中に夫婦が購入した家、車、保険、投資信託、株などの財産を、誰が取得するのか決める必要があります。
離婚時の財産分与で考えるべきことは、「どの財産を」「どんな割合で」「どう分けるか」ということです。

1.財産分与とは?
財産分与には以下の3つの種類があります。
①清算的財産分与…夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の分配
夫婦が、婚姻中に取得した財産を、それぞれの寄与度を考慮して、平等に分けるというのが清算的財産分与です。
分与割合は、原則として2分の1としています。
実務上は、この清算的財産分与を中心に夫婦の共有財産を分けています。
②扶養的財産分与…離婚後の生活保障
離婚後に、年齢や職業や病気などを踏まえて、一方が経済的に困窮するなどの特別な事情があるような場合には、生計の維持を目的として認められるのが扶養的財産分与です。
ただし、離婚後に、夫婦に扶養義務はなくなるのが原則なので、扶養的財産分与は、清算的財産分与の補充として、特別の事情がある場合に限り、限定的に認められているものです。
③慰謝料的財産分与…慰謝料的要素を含めた財産分与
慰謝料と財産分与は、別の項目としてそれぞれ請求ができますが、それらを区別せずに一体として財産分与に慰謝料を含めて請求することを慰謝料的財産分与といいます。
2.財産分与の対象はどこまで?

まず、離婚時に「どの財産を」分けるかをみていきましょう。
(1)財産分与の対象となるもの(共有財産)
離婚時の財産分与では、「婚姻後に夫婦が協力して形成、維持してきた全ての財産」が名義を問わず対象になります。
財産分与の対象には、現金(預貯金)、家、自動車、家財道具、有価証券、保険解約払戻金、会社の株などあらゆる財産が含まれます。
生活費が不足したためにした借金や住宅ローンなど、マイナスの財産も対象になります。
(2)財産分与の対象とならないもの(特有財産)
共有財産の対象は「婚姻後に形成した財産」ですので、「婚姻前から所有していた個人の財産」は対象にはなりません。
また、「夫婦が協力して形成、維持」した財産でなければならないので、個人が相続や贈与で取得した財産も対象に含みません。
(3)財産分与の注意点
ただし、次の2点に注意が必要です。
まず、夫婦以外の名義の財産も実質的に夫婦の財産といえるものは対象になることがあります。
たとえば、夫婦が子どもの将来を考えて、子ども名義の預貯金口座にお金を貯めていた場合などです。
そして、将来もらえるものも対象になることがあります。
たとえば、退職金も財産分与の対象となることがあります。
■あわせて読みたい
退職金のついてはこちら>>>『財産分与における退職金(1)』
3.財産分与はどのくらいもらえるの?
次に財産を「どんな割合で」分けるかについてみていきましょう。
財産は、夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度を考慮して分配することになります。
「自分が働いて得た給料だけで財産を築いたから、専業主婦の妻には何も与える必要はない」
「共働きなのに家事は全て私がやっていたのだから私のほうが多くもらえるのは当然」
といった方もいらっしゃいますが、財産形成へのそれぞれの貢献度は、原則的には2分の1ずつ分けることが一般的です。
無収入の専業主婦であっても、「夫が仕事をしている間、妻が家事や育児をして家庭内を支えたので、財産が形成できた」とも評価できるため、収入がないことが直ちに財産形成への貢献度が低いということにはならないのです。
もちろん財産分与の割合は、各夫婦の事情によっても異なりますので、「自分の方が相手よりも財産形成への貢献度が高い」という場合には、その根拠を示すことにより、2分の1ルールが例外的に修正されることもあります。
また、協議や調停でお互いの合意があれば、2分の1ルールに縛られずに、合意した内容で自由に財産を分けることができます。
4.財産分与の方法は?
最後は、財産を「どう分けるか」についてみていきましょう。
現金の場合には、分け方は簡単ですが、財産に家、自動車、家財道具、会社の株など、色々なものが含まれると、複雑になってきます。
たとえば、不動産は、2分の1ずつの共有状態にすることも可能ですが、離婚後、夫婦は別々に生活することになるので、不動産を共有名義にするメリットは、あまりありません。
しかし、銀行などから住宅ローンの借入れをしている場合は、通常、不動産を担保に借入れをしているので、残ローンの完済前に、夫婦間といえども勝手に名義変更ができないことが多いことです。
そのため、残ローンがある不動産の名義変更は、住宅ローンを借りた銀行などに、離婚に伴う財産分与のために不動産の名義変更が可能か確認する必要があります。
不動産に住宅ローンが残っていると、残ローンをどちらが負担するか、他方が連帯保証人になっている場合に新たに連帯保証人を立てるかなど、様々な点を検討する必要が出てきます。
■あわせて読みたい
離婚時の住宅ローンについてはこちら>>>『離婚した場合、住宅ローンはどうなる?』
また、財産分与による税金の問題や、相手が約束どおりに支払いをしなかった場合の強制執行についても考慮しなければなりません。
財産分与の決めたかは、次のようになります。
(1)協議(話し合い)
協議(話し合い)ができる場合には、まずは協議により財産分与を決めることになります。
双方の所有する財産の項目や評価を確認し、財産分与の割合や分配方法について話し合います。
協議内容は、離婚協議書や公正証書にして残しておきましょう。
公正証書を作成する場合には、強制執行認諾条項を入れておくと、万が一、相手からの財産分与の支払いが滞った場合でも、すぐに強制執行(預貯金や給与の差し押さえなど)をすることができるので安心です。
■あわせて読みたい
強制執行についてはこちら>>>『強制執行について』
(2)調停
話し合いで、財産分与の取り決めができない場合には、家庭裁判所へ調停を申し立てます。
離婚前であれば「夫婦関係調整調停(離婚)」、離婚後であれば「財産分与請求調停」を申し立てます。
(3)訴訟・審判
調停でも合意に至らなかった場合には、離婚成立前の場合は、離婚訴訟を提起し、裁判の中で財産分与の金額を決めることになります。
他方、離婚成立後に、財産分与請求調停の申立てをして合意に至らなかった場合には、審判手続きに移行し、最終的には裁判官に判断してもらうことができます。
5.財産分与の請求はいつまで?
財産分与は離婚の話し合いと同時に取り決めることが多いですが、財産分与の取り決めをしないまま離婚した場合でも、後から改めて財産分与について話し合うことも可能です。
ただし、離婚が成立してから2年以内という請求期限がありますので注意が必要です。
6.離婚時の財産分与は弁護士に相談しましょう

こういった複雑な財産分与は、双方の主張がぶつかり合い、協議でまとまらないことが多々あります。
また、あとになって知らされていない財産が出てきた、支払いの約束を守ってもらえないなどのトラブルも発生する可能性があります。
離婚時の財産分与を円滑に進めるためには、弁護士の交渉力と法律知識が不可欠です。
当事務所では、離婚チームを組織して、弁護士同士での知識やノウハウの共有を行っています。
また、離婚時の財産分与に関して多くの実績を有しています。
「交渉で、相手が住宅ローンを負担しながら、私が家に住み続けられることになった」
「最初に相手から提示をされていたものの倍以上の金額の財産をもらえることになった」
などの事例もあります。
財産分与でお困りの際は、当事務所にご相談ください。