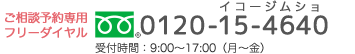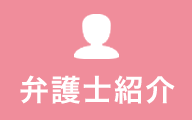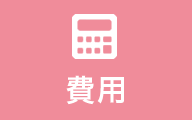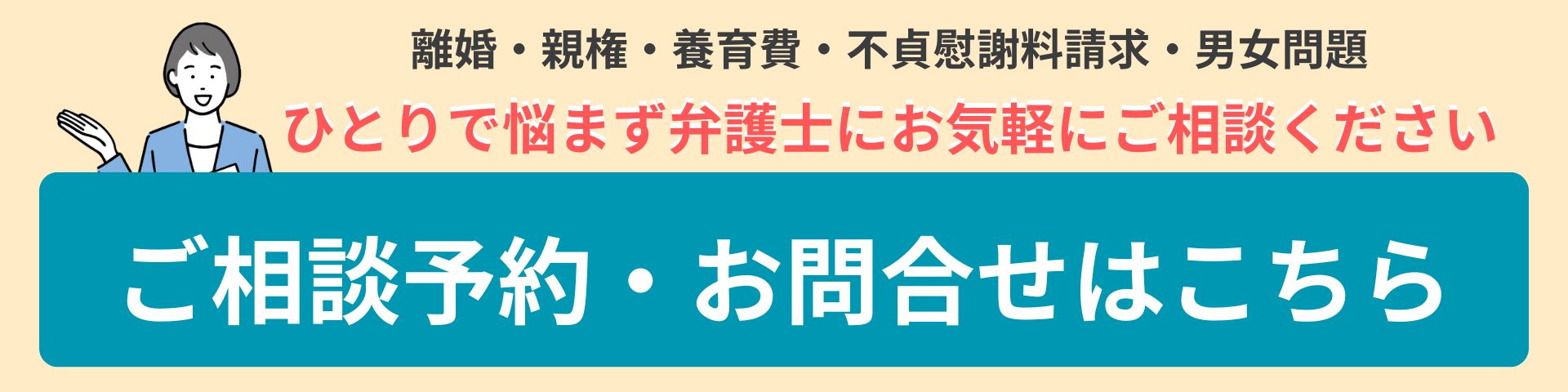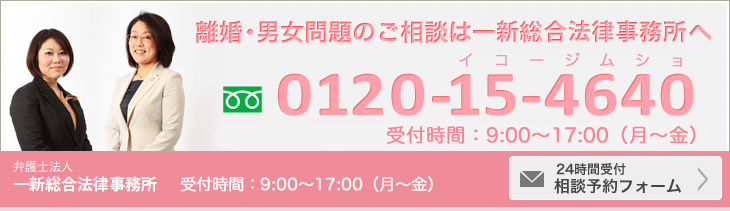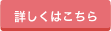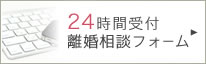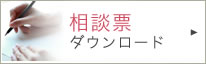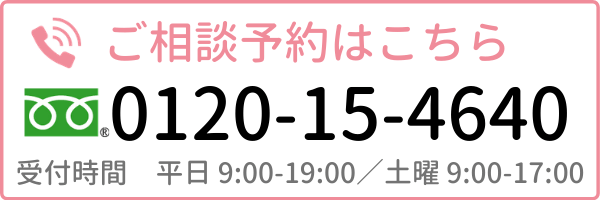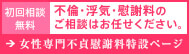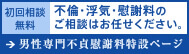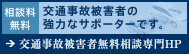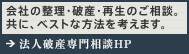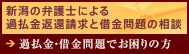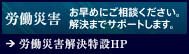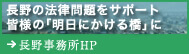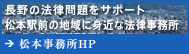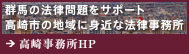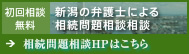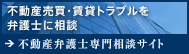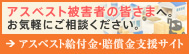不倫相手の女性を妊娠させてしまった!取るべき対処法と注意点

不倫相手の妊娠が発覚したとき、その子どもを出産するかどうか、妻との関係はどうするのかなど、今後の人生の選択について決断を求められることになり、不安に襲われるかもしれません。
大切なことは、妊娠に対して事実確認を行い、相手の女性と今後の方針についてしっかり話し合うことです。
本記事では、不倫をしている男性の立場から、不倫相手の妊娠が発覚した際に求められる対処方法や、注意すべき点について解説します。
相手女性の心身の状態や意思を尊重しつつ、自らの家庭状況とも照らし合わせ、誠実に行動することを心がけましょう。
1.不倫相手の女性を妊娠させてしまった場合の対処法
まずは不倫相手から妊娠を告げられた際に、取るべき行動について解説します。
冷静さを欠くことなく、まずは事実を確認し、今後の対応を考える姿勢が求められます。
妊娠の真偽を病院で確かめる
不倫相手の女性から妊娠を告げられたときに最初に行うべきは、妊娠しているかどうかを自分できちんと確認することです。
相手が勘違いしている、または虚偽の可能性も少なからずありますので、相手の話だけを鵜呑みにせず、可能であれば産婦人科等に付き添い、診断書など正式な医療機関の証明をできるだけ早めに得るようにしましょう。
妊娠検査薬の結果は一つの目安ですが、確実に判断するには産婦人科で診断を受けることが不可欠です。
早期に発見ができれば出産・中絶について話し合う時間的余裕も生まれます。
妊娠初期は母体の健康状態、精神面でも不安定であり、相手女性に特に配慮する必要がありますので、子どもをどうするのかについての話し合いに要する時間的余裕は多いほうがよいでしょう。
また、意図せずに妻や家族に自身の不貞行為が発覚する恐れがありますので、病院を受診した際の領収書等の扱いには気をつけましょう。
妊娠週数や母体の健康状態を把握する
病院で妊娠を確認したら、現在の妊娠週数や相手女性の健康状態をしっかりと把握しましょう。
妊娠22週以降になると人工妊娠中絶手術を受けることができなくなりますので、なるべく早く今後についての話し合いを行う必要があります。
また、妊娠中のトラブルは週数によって発生しやすいものが異なるため、妊娠週数によって相手女性へ求められる配慮が異なってきます。
妊娠した子どもの今後について話し合う
妊娠の事実が確定すると、まず出産をするか中絶をするかをできるかぎり早めに決断しなければなりません。
どちらを選択しても、相当な心身の負担や金銭的な責任がかかるため、あらかじめ情報収集を行ったうえで相手女性と十分に話し合うことが肝心です。
決断が遅れると中絶が難しくなるケースもあるため、迅速かつ慎重に行動することが求められます。
今後について話し合う際は、今後どうしたいのか自分自身の気持ちとしっかり向き合うと同時に、相手の気持ちにも配慮しましょう。
単なる浮気だったとしても、急に連絡を絶ったり、話し合いから逃げたりする対応は絶対にしてはいけません。
話し合いを避ける行為は何の解決にもならないばかりか、人工妊娠中絶手術を受けられる期限を逸してしまったり、後になって相手女性から慰謝料請求をされたり、職場や家庭に不倫関係を暴露されるなどのトラブルが発生する可能性もあります。
2.妊娠発覚後の選択肢
次に、妊娠が判明した後に中絶または出産という大きな分岐点を前に、考えるべき選択肢について解説します。
子どもを出産する場合
話し合いの結果、子どもを出産することを決めた場合についてです。
出産するにあたり子どもを認知するかどうか、不倫相手との関係を継続するのか、妻と離婚するのか、生まれてくる子どもの養育費の取り決めや出生後の生活環境の準備などについて決めなければなりません。
認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)について、子と父親との間に法律上の親子関係を成立させる制度です。
子どもを認知すると、自分と子どもの親子関係が法的に証明されます。
あなたの戸籍に入るわけではないですが、認知した事実は戸籍に記載されるため、妻に不倫の事実を隠すことは難しいでしょう。
また、認知をすることで、その子どもに対して養育費の支払い義務が発生します(民法877条1項)。
養育費の支払いの有無や、金額、支払い方法についても、相手女性としっかりと取り決めを行いましょう。
相続の面でも、認知した子どもはあなたの法定相続人となり、自身の財産を相続する権利を持つことになります(民法887条1項)。
嫡出子(婚姻関係にある男女の間に産まれた子)も非嫡出子も相続分に関しては同じ権利を有します。
認知は出産後だけでなく、出産前であっても胎児認知をすることができます(民法783条1項)。
胎児認知を行えば、万が一出産までに父親が死亡してしまったなどの事態が起こったとしても、生まれてきた子どもは父親の相続を受けることができます(民法886条1項)。
・認知しない場合の注意点
子どもは出産するが認知をしないことを選択すると、法的に子どもとの親子関係が成立しないことになります。
認知をしなければ生まれてくる子どもに対しての責任から逃れられたように思えるかもしれませんが、出産後に不倫相手や、生まれてきた子ども自身から「強制認知」の手続きをとられる可能性は残ります。
強制認知とは、婚姻関係にない子どもの父親が認知をしてくれない場合に、家庭裁判所に「認知調停」や「認知の訴え」を行い、父親に対して認知を求めることです。
DNA鑑定などが行われ、父子関係が認められれば裁判所により強制的な認知がなされます。
認知が認められれば、出生までさかのぼって法律上の親子関係が発生することになり、同時に養育費の支払い請求が可能となります。
・ダブル不倫の状況で出産する場合
あなたの不倫相手の女性も既婚者であった場合は、法律上の父親についての考え方が難しくなってきます。
民法上の考え方として、子は、法律上の婚姻関係にある男女間に生まれた子(嫡出子といいます)と、そうでない子(非嫡出子といいます)に、分類されています。
妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子(嫡出子)と推定されます(民法772条1項)。
つまり、婚姻中に妻が妊娠した子が、不倫相手の子であったとしても、夫の子とみなされてしまい、法律上の親子関係が生じてしまいます。
不倫相手女性の夫側が、妻の不倫の事実を知り、生まれてきた子(嫡出子)との親子関係を争いたい場合、嫡出否認の訴えを行い、嫡出子についての親子関係を争う裁判手続きをとることになります。
嫡出否認の訴えは、子の出生を知ったときから3年以内に提起しなければなりません(民法第777条)。
訴えがなされると、DNA鑑定を行い、血縁上の親子関係がないことが立証されれば、(不倫女性側の)夫との法律上の親子関係が否定されることになります。
【法改正|令和6年4月1日】嫡出推定規定について
民法772条の嫡出推定規定について、令和6年4月1日に法改正が行われました。
改正前の規定では、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」と定められていました。
そのため、離婚等の日から300日以内に元夫以外の者との間の子を出産した女性が、戸籍上、血縁上の父でない人の子と記載されるのを避けるため、出生届そのものを提出せず、子どもが無戸籍となるという問題が発生していました。
改正後の規定では、「離婚後300日以内の出産の場合でも、母が再婚後に出産をしている場合には、例外的に再婚した夫の子どもとみなす」という内容に改正されました。

中絶する場合
次に中絶を選択する場合に必要な費用や条件、配慮すべき点について説明します。
自身が妻との離婚を考えていない、不倫相手が出産を望んでいないなどの場合には、人工妊娠中絶手術を受けてもらう選択肢があります。
人工妊娠中絶手術は、法律上は妊娠21週6日までとされていますが、あなたが子どもの出産に同意していなくとも、相手に強制的に人工中絶手術を受けさせることはできません。
また、人工妊娠中絶手術は女性側にとって肉体的・精神的に多大な負担がかかるため、相手への配慮と責任ある行動が求められます。
・中絶が可能な条件
妊娠中手術は妊娠21週6日までとされており、22週を過ぎると妊娠中絶自体が不可能となります。
また、誰でも手術が受けられるわけではなく、母体保護法という法律によって人工妊娠中絶が認められる条件は決められています。
条件とは、①母体の健康上、妊娠の継続または分娩が困難な場合または経済上の理由がある場合、②暴行もしくは脅迫によって性交の抵抗・拒絶することができなかった場合、の2つです。実際には「経済上の理由」が広く理解されているため、中絶を希望する女性が条件を満たさないために人工妊娠中絶手術を受けられない事態は極めてまれです。
・中絶費用について
人工妊娠中絶手術は健康保険適用外となります。
手術費用は妊娠週数によっても異なってきますが、相場の目安として妊娠初期(~11週6日目)では10万円~20万円、妊娠中期(12週目~21週6日目)では30万円~50万円程度となります。
中期中絶手術になると、胎児がそれだけ大きくなっているので、初期中絶と違う方法で手術を行わねばならず、入院が必要になりますし、母体への負担も大きくなります。
人工妊娠中絶手術費用の負担割合については、妊娠は双方の責任であるという考えから、半額ずつ負担するケースもあります。
一方で、中絶に伴う相手女性の身体的・精神的負担を考慮して、男性側が全額を負担するケースもあります。
いずれにしても、誠意を持って対応することが重要であり、後のトラブル回避にもつながります。
3.妻との今後の関係について
既婚者が不倫で相手女性を妊娠させてしまった場合、相手女性との関係だけでなく、配偶者である妻との夫婦関係についても考える必要があります。
離婚を検討する場合
あなたが不倫をして、不倫相手との間に子どもを授かっているケースでは、夫婦関係の破綻について「有責配偶者」として夫側にその責任が問われる可能性が非常に高くなります。
法律上、不貞行為をした側である有責配偶者からの離婚請求は原則として認められていません。
そのため、あなたが離婚をしたいと考えた場合でも、妻が離婚を受け入れなければ、すぐに離婚することはできず、離婚成立までに多くの時間を要するケースが少なくありません。
◆有責配偶者[ゆうせきはいぐうしゃ]とは
離婚原因を作り、婚姻生活を破綻させた配偶者のこと。
原則有責配偶者からの離婚請求には特別な要件(別居期間・未成熟子の存否・離婚後の生活保護)が必要となります。
・慰謝料請求について
夫が不倫をし、不倫相手の女性が妊娠しているとなれば、妻の受ける精神的苦痛は計り知れません。
不倫相手の妊娠が原因で離婚に至った場合、妻側から通常よりも高額な慰謝料請求をされる可能性があります。
一般的には数十万円から数百万円ほどの慰謝料が発生すると考えられます(目安としては50万円~300万円程度)。
ダブル不倫や長期間の不倫など、悪質性が高いほど慰謝料が高額になる可能性があります。
具体的な金額は裁判所の判断や話し合いの結果によるため、早めに弁護士を通じて見通しを立てることが重要です。
また、離婚に至ったかどうか、不倫相手の出産や認知の有無にかかわらず、妻は不倫相手の女性に対しても不貞行為を理由とした慰謝料請求ができることも覚えておきましょう。
・ダブル不倫の場合の慰謝料
不倫関係にある双方が既婚者、いわゆるダブル不倫をしていた場合には発生する慰謝料にも気をつけなければなりません。
双方の夫婦が離婚をしない場合には、お互いの慰謝料請求が相殺されるかたちとなり、慰謝料が発生しない可能性もあります。
一方で、双方の夫婦が離婚する場合、不倫をした側は(男女ともに)浮気をされた側の配偶者から離婚慰謝料、不倫相手の配偶者からは不倫慰謝料を請求される可能性があります。
・婚姻費用について
夫婦には生活保持義務があり、収入が高い方が低い方の生活費を負担しなければなりません。
もし妻が専業主婦やパートなどあなたより収入が低い場合には、別居開始から離婚が成立するまでの間は、あなたは妻に対して婚姻費用を支払い続ける必要があります。
離婚協議が長期化すれば、自身の生活費と妻の生活費を支払っていかなければならず、相当の金銭的負担がかかることになるでしょう。
・養育費について
妻との間に子どもがいる場合には、離婚したからといって子どもに対する扶養義務がなくなるわけではありません。
子どもが経済的・社会的に自立するまで(裁判や家事審判になった場合には、一般的に20歳までとされる傾向にあります。)は養育費の支払わなければならないとされています。
養育費の金額をいくらにするのか決める際の根拠となるものは、父母それぞれの年収や、子どもの人数・年齢などがあげられます。
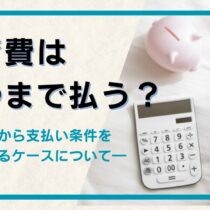
離婚せずに夫婦関係を継続する場合
妻との夫婦関係を継続したいと考えた場合は、まず信頼関係の回復に向けた話し合いが不可欠です。
不倫の事実を隠して夫婦関係を継続することは困難な場合もあり、いずれ妻にその事実が知られることも想定しなければなりません。
不倫していた事実が判明し、妻側から離婚請求をされた場合には、法定離婚事由(配偶者に不貞な行為があったとき)があるために、あなたが離婚を望まなくても離婚が成立してしまいます。
◆法定離婚事由とは
離婚裁判においては、夫婦の一方が離婚の訴えを提起するための離婚原因を定めています(民法770条1項各号)。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。※2
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
※2:令和6年5月、前記民法等の一部を改正する法律が成立、公布されました。公布から2年以内に施行される予定です。
改正法では、770条第1項4号「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」は削除されます。
・不倫相手が出産した場合の養育費
妻と離婚せずに、不倫相手の子どもを認知する選択をする場合には、認知した子どもに対して養育費の支払い義務が発生します。
養育費の取り決めについては弁護士などの専門家に相談しましょう。
4.不倫問題を弁護士に相談するメリット
不倫中の相手女性の妊娠が発覚した場合、まずは冷静に妊娠の事実を正確に確認し、その上で出産や中絶のいずれを選択するかを相手女性と慎重に話し合うことが重要です。
あなたの対応次第では、法的なリスクが発生する危険もありますので真摯な対応が求められます。
また、不倫相手が妊娠してしまった場合、不倫関係にある当事者間だけでなく、妻や子ども、家族にも多大な影響を及ぼす問題となります。
妻との離婚を視野に入れる場合は、離婚協議の長期化だけでなく、不貞慰謝料額や財産分与など、通常よりも厳しい条件になることを見据えて話し合いを行う必要があります。
不倫問題に直面しているときは、当事者同士の感情が激しく高ぶり、冷静な判断を下しにくい状態に陥りがちです。
また、不倫を原因とした男女間問題や慰謝料請求、離婚や財産分与といった複雑な法的手続きは、自分ひとりで進めていくのは容易ではありません。
弁護士に相談することで、相手との交渉や必要書類の作成まで、法的リスクを避け、円滑に進めることができます。
そして、法的根拠に基づく説明と第三者の客観的視点からアドバイスにより不安が和らぐこともあるでしょう。
トラブルを最小限に抑えるためにも、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
男女問題・離婚問題でお悩みの場合は、まずは一新総合法律事務所までお気軽にご相談ください。