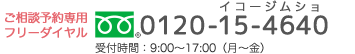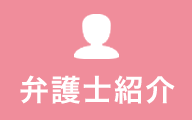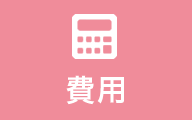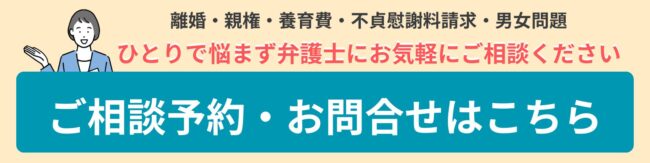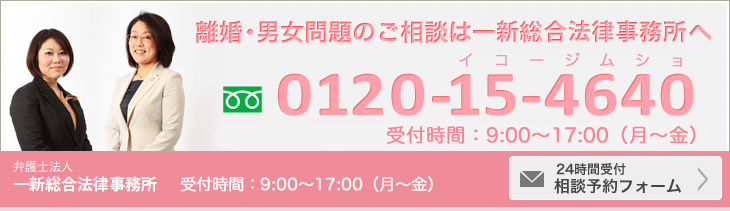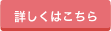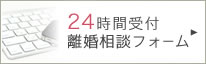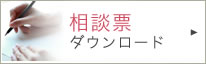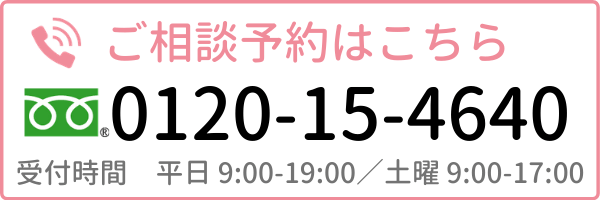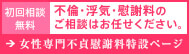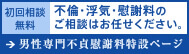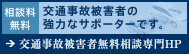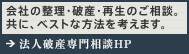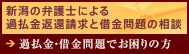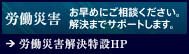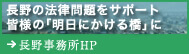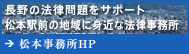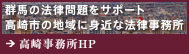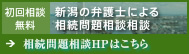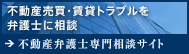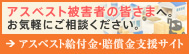これから離婚を切り出したい【離婚の切り出し方と注意点】
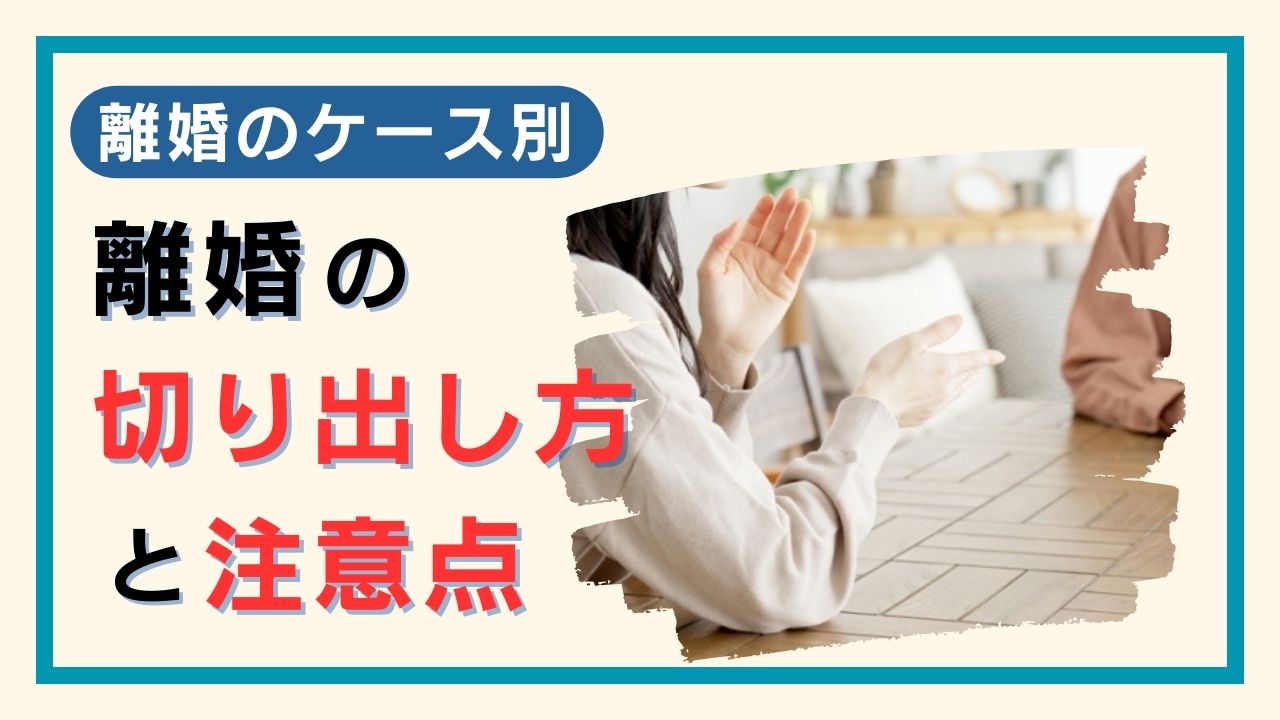
離婚したいと考えた時、最初に問題となるのが、そのことをどのように配偶者に切り出すかということです。
相談時、次のような質問を受けることがあります。
「離婚したいという気持ちを直接言わなきゃダメですか?」
離婚の切り出し方に、こうしなければならないという法律的な決まりはありません。
また、離婚したい理由や、子供のあり・なし、婚姻期間の長さなど個々の事情によっても、離婚の切り出し方も変わらざるを得ないでしょう。
ただ、大切なのは「離婚したい」と伝えて終わりではなく、そこは始まりであり、その後に離婚協議をしなければならないということです。
円満な離婚のためには、相手との話し合いをどう進めるかを考えることが大切です。
本記事では、離婚を切り出す前に考慮すべきポイントやタイミング、ケース別の伝え方や注意点などを解説します。
1.離婚を切り出す前に
自分の気持ちや理由の整理
離婚を切り出す際には、相手の意見を尊重しつつも、自分の希望を明確に伝える姿勢が求められます。
そのため、自分がどのような理由で離婚を望むのかを紙に書き出してみるなどして自分の気持ちを冷静に掘り下げる作業が大切です。
感情に任せて離婚を進めてしまうと、後になって後悔する可能性があります。
事前に冷静に自分の気持ちを整理しておくことで考えがまとまり、話し合いを進めやすくなるでしょう。
相手の性格や状況を理解する
離婚を切り出すときには、相手の性格や現在置かれている状況に配慮しましょう。
精神的に不安定な時期や仕事で忙殺されているときに突然話を持ち出すと、相手からの反発を招き、かえって話し合いが難航してしまう恐れがあります。
相手の性格や状況を見極め、お互いが冷静に対話できる環境を整える配慮をしておくことで、円滑な話し合いにつながりやすくなるといえます。
離婚後の生活設計と経済的自立の準備
離婚をしたいことを伝えた場合、配偶者の反応が予想通りとは限りません。
普段温厚な配偶者が、離婚したいと伝えた途端、激しい拒否反応や警戒が始まるケースもあります。
ときには、予想外の反応でそのまま別居せざるを得なくなるケースもあります。
万が一のリスクを考え、急な別居に備えて重要なもの(実印、通帳、年金手帳など)はすぐに持ち出せるようまとめておきましょう。
離婚後、どのように生活していくかを具体的にイメージし、仕事や住居、生活費等の経済面の確保に向けた事前準備をしてから切り出すといった今後の生活に備えておくという視点も重要です。
子どもや家族への影響を考える
お子さんがいらっしゃる場合は、離婚を切り出すことによる子どもの精神的負担を考慮し、子どもの立場にも配慮すべきです。
特に未成年の子どもがいる場合、現行法では離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ、離婚自体ができないことになっていますし(※1)、離婚後に子どもの生活環境が大きく変化することは少なくありません。
子どもの気持ちに配慮して、離婚の話を子どもの前ですることは避け、登校している時間帯や、親族に預けるなどして夫婦で落ち着いて話し合える日時や環境を整えましょう。
家族や親族への影響も大きいため、急に具体的な話をするのではなく、段階的に状況を説明する姿勢が望ましいでしょう。
思春期や受験期など、子どもの年齢にも配慮し、離婚のタイミングについても慎重に検討をする必要があります。
ーーーーーーーーー
\共同親権について法改正があります/※2025年3月更新
※1:令和6年5月、共同親権の導入等を内容とする民法等の一部を改正する法律が成立、公布されました。公布から2年以内に施行される予定です。改正法では、協議離婚の際、父母の一方のほか、父母の双方を親権者と指定することができるようになります。
詳しくは下記▼関連記事▼でご紹介しています。

離婚条件を検討・夫婦の財産を把握する
離婚に際しては、通常、①親権、②養育費、③財産分与、④慰謝料、⑤年金分割、⑥面会交流について協議して決めていきます。
最初からすべてについて自分の考えを伝える必要はありませんが、条件など全体像が分からない中では検討が進みにくいといえます。
配偶者に離婚を検討してもらうためには、離婚したいということだけを伝えるのではなく、それに伴う条件について自分なりの考えや希望をある程度はまとめておく必要があります。
特に財産分与、養育費などお金に関することは、離婚後お互いの生活基盤となる重要な事柄になりますので、夫婦の共有財産やお互いの収入について把握し、だいたいどのくらいの財産分与や養育費の支払いが見込めるのかを把握しておきましょう。
不倫・DVなどの場合は証拠を集める
不倫やDVなどの深刻な事情が離婚の原因となっている場合は、証拠を集める前に離婚を切り出してしまうと、証拠隠滅の恐れがあります。
離婚話をする前に、DVの音声データ、けががあった場合の写真や診断書、不倫の証拠となる写真や不倫相手とのLINEのやり取りがわかるスクリーンショット、場合によっては浮気調査を実施するなど、無理のない範囲で客観的な証拠を集めておくことが大切です。
証拠の有無やその証拠の内容によって、慰謝料請求の可否やその請求金額等の条件が大きく変わる場合があり、公平な話し合いの基盤を作るうえでも欠かせません。
まずは自分の状況を冷静に整理し、法的にどのような手続きを踏むべきか弁護士に相談することをおすすめします。
2.ケース別の離婚の話し合いと進め方
離婚理由はそれぞれの夫婦によって異なります。
性格の不一致や、不倫、金銭感覚の違いなど、離婚原因によって離婚の切り出し方も異なります。
以下のケースを参考に、話し合いが円滑に進むように準備しましょう。
性格の不一致の場合
性格の不一致が理由で離婚を切り出す場合、忘れてはならないポイントは、相手が自分と同じように感じているとは限らない点です。
その場合は、相手のことを否定するのではなく、なぜ自分が離婚したいと思うに至ったのかについて具体的な生活エピソードを用いて整理して説明すると理解が得やすくなります。
例えば、子どもの教育方針が合わない、金銭感覚が合わないなど価値観の感じたときの自分の想いを伝えます。
明確な理由を説明できないと、相手からはただのわがままではないかと思われ、離婚するほどのことではないと話し合いに応じてもらえなくなる場合もあります。
性格の不一致のみを理由に離婚をしたい場合(更に別居期間も短い場合など)、話し合い(協議)や調停で離婚に合意できずに裁判に発展してしまうと、直接的な法定離婚事由(民法770条1項各号)に該当しないため裁判離婚を成立させることが難しくなりえます。
相手の気持ちも考慮しながら、真剣に離婚したいと考えているという自分の気持ちを冷静に伝え、話し合い(協議)で離婚の合意を目指すこともとても重要になります。
【法定離婚事由とは】
離婚裁判においては、夫婦の一方が離婚の訴えを提起するための 離婚原因を定めています(民法770条1項各号)。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(※2)。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
以上の5つの事由のいずれかに該当しない場合は、裁判において離婚を成立させられる可能性が低くなります。
ーーーーーーーーー
※2:令和6年5月、前記民法等の一部を改正する法律が成立、公布されました。公布から2年以内に施行される予定です。改正法では、770条第1項4号「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」は削除されます。
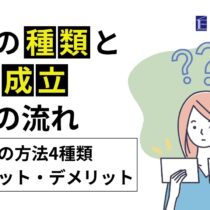
不倫や浮気が原因の場合
不倫や浮気が原因の場合は、事実関係をしっかり確認し、可能であれば証拠を確保しておく必要があります。
話し合いの場では、感情的な非難を繰り返してしまいがちですが、公平な協議を進めるために具体的な状況を整理して冷静な話し合いを心がけましょう。
慰謝料や財産分与の条件に関わる要素でもあるため、弁護士に相談して法的な手続きも視野に入れましょう。
DVやモラハラが絡む場合
DVやモラハラ被害がある場合は、自身や子供の身体的・精神的な安全を最優先に行動する必要があります。
信頼できる身近な人や専門機関に相談し、身を守ると同時に証拠を確保することが大切です。
離婚を切り出すことで更に暴力や暴言を受ける危険性があるので、直ぐに助けも求められないような密室二人きりの状況で直接切り出すことはお勧めできません。
むしろ、家を出て心身の安全を確保した上で、メールや手紙、あるいは弁護士を通じて離婚の意向を伝えていくことを検討することも必要でしょう。
【関連記事】モラハラが理由で夫・妻と離婚したい!特徴と必要な準備
セックスレスが原因の場合の話し合い方法
セックスレスは夫婦間でも切り出しづらい問題のひとつで、コミュニケーション不足からさらに溝が深まることもあります。
恥ずかしさや遠慮からお互いに本音を言えない場合が多いですが、相手を責めるよりも、自分の素直な気持ちを伝え一緒に問題解決を模索することで夫婦の関係性が良い方向に変化することもあります。
ほかに好きな人ができた場合
不倫に至ってはいないが、夫・妻以外に好きな人ができたため離婚したい場合、その気持ちだけでは不貞行為には該当しません。
しかし、配偶者から好きな人ができたから離婚したいと言われた相手の気持ちを考えると、正直に伝えるのは避けた方がよい場合もあります。
不貞行為ありなしに関わらず、自分から気持ちが離れてしまったことを聞かされることはただ相手を傷つけ、状況を硬直させてしまう恐れがあります。
離婚の話合いにおいては条件等の面で不利になることもありえますので、どのように切り出すかについて、よく検討した方が良いでしょう。
すでに話し合いが困難な場合
お互いが冷静な話し合いができない、もしくは別居期間が長いなどすでに婚姻関係が完全に破綻している、感情的な対立が深刻化している場合は、自分から離婚を切り出すのではなく、弁護士など第三者を交えることを検討するべきです。
弁護士が間に入ることで、公正な視点で問題の整理や交渉を進めることができる場合もあります。
3.離婚を切り出す具体的な手順と伝え方

適切な話し合いの場を設ける
できるだけ二人きりになる場所での話し合いは避け、第三者の目が少し届く程度の場所を選ぶと安心です。
お互いに落ち着いて話せる場所であれば、強い口論や暴力が発生するリスクを抑えることができ、自分の考えをしっかりと伝えられることですれ違いを防止することもできます。
二人だけで話す自信がない場合は、親族や信頼できる友人などに同席してもらうなどしましょう。
突然の切り出しによる混乱を防ぐ
何の前触れもなく離婚を切り出されると、相手はパニックに陥りやすくなります。
事前にそれとなく「話し合いたいことがある」と伝えておくだけでも、相手が心構えを持つことができ、切り出した段階での混乱防止につながり、話合い自体を受け入れてもらいやすくなります。
感情的にならず冷静に伝える
離婚の切り出し方は、できるだけ自分の気持ちを客観的に伝えることを意識することが大切です。
感情に任せて相手を責める言葉ばかりを使うと、相手の防衛本能を刺激してしまいます。
冷静さを保つことで、相手に対し離婚の意思が伝わり、話し合いもスムーズに行いやすくなるでしょう。
誰でも離婚を切り出す場合には、気持ちが前面に出てしまって、感情的になりやすい傾向にありますので、前述したように、離婚理由や離婚条件をメモなどで整理した上で、自分の考えを順序立てて冷静に伝えるように心がけましょう。
また、夫婦のどちらか一方が専業主婦(専業主夫)やパートなど自身より収入が安定していないような状況の場合には、離婚後の生活に対する妻(夫)の不安をできる限り減らすことが離婚成立をスムーズにさせるポイントになります。
子供の養育費や財産分与、慰謝料の条件について、妻(夫)に有利なものとなるような提案をすることも検討しましょう。
対面での伝え方と適切な言葉選び
相手を一方的に攻めるような言い方は避け、「自分はどう感じていたのか」といったように自分の気持ちを主語にして説明する姿勢が望ましいです。
どこが合わないと感じたのか、何が辛かったのかを具体的エピソードとして話すことで、相手も受け止めやすくなります。
また、相手の言い分や気持ちを尊重する姿勢を忘れてはいけません。
お互いにしっかりと気持ちを伝える中で、夫婦関係修復の可能性を模索できるかもしれません。
電話、メール・手紙・LINEでの伝え方
対面であれば表情や声音から相手の反応をうかがえますが、それだけに感情的になりやすい面もあります。
冷静に話し合う自信がない、すでに別居中である、DV被害があるなどの場合には、電話やメールなどの通信手段を利用して相手に伝える方法も検討しましょう。
ただし、通信手段を使用する場合、直接対面するストレスを軽減できる半面、真意や感情が伝わりづらいなど誤解が生じやすいため、一層言葉の選び方に注意が必要です。
夫婦の関係性や状況を考慮し、最も誠意を持って伝えられる方法を選ぶことが大切です。
即断を避け、冷静に次のステップを話し合う
離婚は人生の大きな分岐点であり、即断すべき問題ではありません。
一時の感情にまかせてすぐに離婚届にサインをすることは絶対に避け、話し合いをするときには焦って結論を出さずに、一度持ち帰って考える時間を設けるなど、冷静さを保つ努力をしましょう。
4.離婚を考えている方へ
離婚は大きな決断であり、ネガティブな面ばかりが目立ちがちです。
しかし、冷静に考えて離婚を決断し、更に必要な準備を経たうえでの離婚はあなたの新たな人生を切り開く選択であり機会でもあります。
離婚の切り出し方を考えるとき、相手への伝え方や子どものケア、離婚後の生活に対する経済的な備えなど多くの不安を抱えることになるでしょう。
離婚について切り出せないままに、既に別居状態になっていて直接当事者からお伝えする機会を逸してしまっているようなケースでは、結果的に弁護士からの手紙で初めて、離婚したいこと、なぜ離婚したいと考えているのかを伝える形となる場合もあります。
当事者間での話し合いの機会なく、弁護士からの手紙で依頼者が離婚したいと考えていることをお伝えすることになった場合には、配偶者から「なぜ事前に直接話がなかったのか」「本当に本人の意向なのか」と反発がでることがあります。
離婚を切り出したからといって、配偶者の納得を得ることは難しいかと思いますが、まずは直接離婚したいことを伝えて協議(話し合い)に入る場合と、そのような機会もなく協議をしていく場合とでは、その後の離婚交渉に違いが出るといえます。
事情によっては直接話をすることが難しい場合でも、手紙で伝える、メールで伝えるなど、きちんと配偶者と話し合う気持ちや姿勢を持っていることを伝える方法がとれないか考えてみましょう。
迅速な解決を望むのであれば、協議でまとまる可能性を摘むことは避けるべきです。
切り出す前に、円滑な協議のために、どうしたらよいのか迷う場合には、ご自身のケースで今後どのように進めていくのが良いのか、離婚の切り出し方も含めて弁護士に一度ご相談いただければと思います。
一新総合法律事務所では、離婚問題に精通した弁護士が対応し、ひとりひとりのお悩みに寄り添いながら丁寧に聞き取りをし、あなたの状況に応じた適切なアドバイスを行います。
慎重な検討と冷静なコミュニケーションを重ねることで、深刻な対立を回避しながら前向きな結論へ近づけるかもしれません。
自分自身の人生設計と相手、そして子どもの将来を踏まえた話し合いを大切にし、一歩ずつ確実に進めていきましょう。
ひとりで悩まずにまずはお気軽にご相談ください。
■関連記事のご紹介