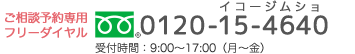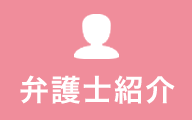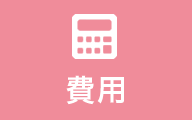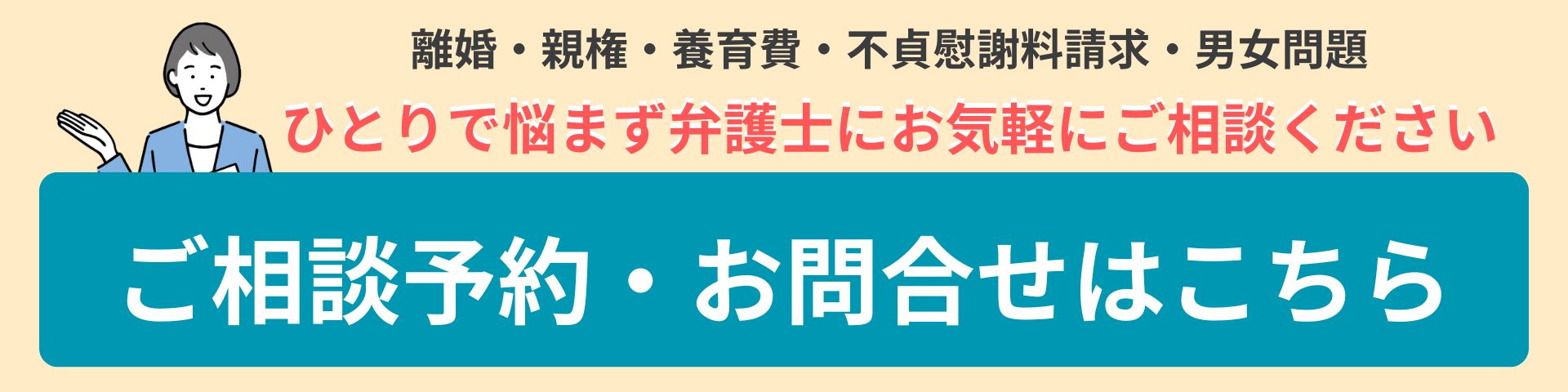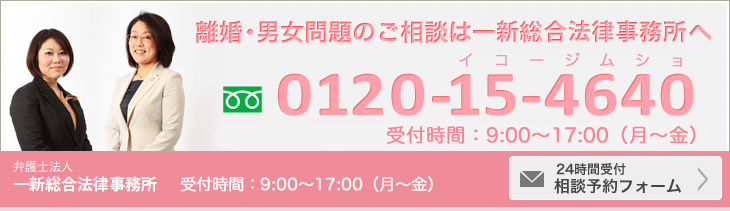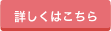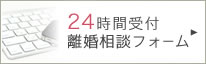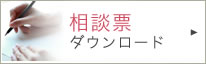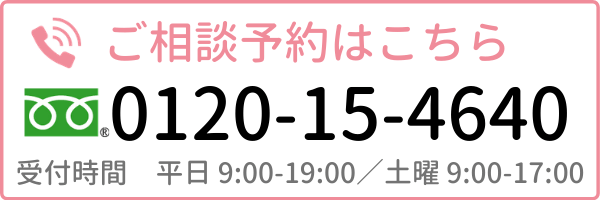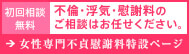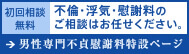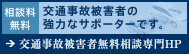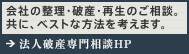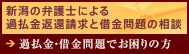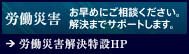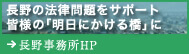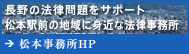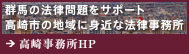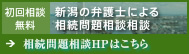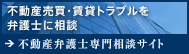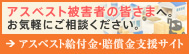離婚で財産分与をしない方法とは?拒否できる条件と注意点を徹底解説

離婚時の財産分与は、夫婦間の大きな争点のひとつです。
場合によっては財産分与をしない、あるいはできるだけ財産分与額を減らしたいと考える方もいるでしょう。
本記事では、財産分与の基本的なルールや対象となる財産の範囲、財産分与をしない方法、注意点までを徹底解説します。
ご自身の状況に沿った選択肢を知り、離婚時の財産分与でのトラブルを防ぎましょう。
1.財産分与とは?その範囲と基本ルール
まずは財産分与の基本的な考え方と、対象となる財産について説明します。
【財産分与の基本ルール】
・原則として2分の1ずつで、夫婦の共有財産を折半する
・双方の合意があれば、合意した割合・内容で自由に財産を分けることができる
・財産分与の対象となる「共有財産」と、対象とならない「特有財産」がある
財産分与では公平な配分が原則
財産分与とは、婚姻中に夫婦が共同で築いた財産を離婚時(または離婚後)に公平に分配する制度です。
財産分与の割合は、原則として2分の1ずつで、夫婦の共有財産を折半します。
婚姻中の資産形成は、収入のような経済的貢献のみならず、婚姻期間の長さ、夫婦が婚姻生活を送る中で担ってきた家事や育児などの非経済的貢献などによるところも大きいと考えられているためです。
例えば専業主婦のケースでは、一方にだけ収入がない状態ですが、家事労働によるサポートが財産形成を支えたと評価され、結果的に夫婦双方で得られた財産は原則として半分ずつ分与されます。
2分の1ルールは原則であり、お互いの合意があれば、合意した割合・内容で自由に財産を分けることができます。
共有財産が財産分与の対象となる
離婚時の財産分与では、「婚姻中に夫婦が協力して形成、維持してきた全ての財産」が名義を問わず対象になります。
これを共有財産といいます。
具体的には、婚姻期間中に形成された預貯金や、婚姻中に購入した家などの不動産、車、株式などの投資商品、さらに生活に使用している家具や家電も含まれます。
生活費が不足したためにした借金や住宅ローンなど、マイナスの財産も対象になります。
【共有財産に含まれるもの】
・金銭や預貯金(給与・ボーナス・事業収入などから形成された預金、名義が夫または妻のいずれであっても対象)
・不動産(住宅、土地、マンションなど。名義が一方でも、婚姻中に取得したものであれば原則対象。※ローン差引評価)
・動産類(家具、家電、車、貴金属、美術品など。購入時期が婚姻中であれば基本的に対象。)
・有価証券、金融商品(株式、投資信託、仮想通貨など。婚姻期間中に取得・運用されたもの。)
・退職金(※離婚時にすぐ支給されていなくても、「すでに支払われることが見込まれている」退職金の一部は対象になることがあります。婚姻期間に対応した按分評価となります。)
・保険(解約返戻金のある生命保険・養老保険など。積立型の場合は解約返戻金の評価額を財産分与に反映。)
・ 私的年金(企業年確定拠出年金など。※公的年金に関する年金分割についてはこちら)
退職金や年金分割については熟年離婚の際に争点になることが多い部分となります。
熟年離婚の財産分与については以下のコラムで詳しく解説していますのでご参照ください。

ただし特有財産は対象外
共有財産の対象は「婚姻後に形成した財産」ですので、「婚姻前から所有していた個人の財産」は対象にはなりません。
また、相続や贈与によって個人が得た財産は「特有財産」として扱われるため、通常は財産分与の対象外になります。
【特有財産】
・婚姻前から所有していた財産
・相続・贈与により取得した財産(実家の不動産、相続した預金など。)

2.財産分与をしないことは可能?
相手方から財産分与を請求された場合、法律上は財産分与請求権が認められるため、原則として拒否することはできません。
ですが、特定の条件や手続きを踏めば分与をしない選択肢も考えられます。
協議で「財産分与なし」に合意した場合
夫婦間で協議の末、財産分与請求権の放棄に合意できれば、財産分与なしでの離婚は可能です。
ただし、合意後に財産内容の情報開示が不十分だったことが発覚したり、後になって一方から無効を主張されたりした場合は、争いになる可能性もあります。
トラブルを未然に防ぐためにも、財産情報の開示をきちんと行ったうえで協議をし、合意した内容を離婚協議書や公正証書に明示しておきましょう。
除斥期間(2年)を過ぎれば請求できなくなる場合がある
離婚後の財産分与請求は、離婚が成立してから2年以内という請求期限があります(民法768条2項)。
これは「除斥期間」と呼ばれるもので、法的に定められた請求期限です。
除斥期間の経過後に相手から財産分与請求をされた場合は、請求を拒否することができます。
特有財産の主張で財産分与の対象を限定する
特有財産について、共有財産と区別できれば、離婚時の分与から除外することができます。
特有財産であることを確実に主張するには、贈与契約書、遺産分割協議書の提示や、婚姻前と後で預金口座を分けておくなどの対策が求められます。
結婚生活を始める時点で自分の所有財産について整理しておくのが理想的です。
実際の離婚調停などでは、特有財産の主張がなされることはとても多いのですが、特有財産であると認められることは、実は簡単ではありません。
曖昧な主張では、裁判などで共有財産とみなされてしまうおそれもあります。
法的な論点も多いので、自分一人で判断せずに弁護士に相談した方がいいでしょう。
夫婦財産契約を締結する方法
民法の規定に則らない夫婦間の財産に関する取り決めをする契約のことを夫婦財産契約といいます。
これは民法上に規定された法的制度で、婚姻前に夫婦財産契約を交わし、財産分与を行わないとの取り決めがあれば、離婚時の財産分与を制限または回避できる可能性があります。
夫婦財産契約は、婚姻前に契約を結び、登記しておく必要があります。
登記がなければ第三者や裁判所に対する効力が限定される可能性があります。
また、原則として後から契約内容の変更や廃止ができない点に注意が必要です。
3.財産隠しや使い込みは危険!リスクを解説
財産分与を避けるために、財産を隠したり、離婚直前に使い込んだりした場合にはどうなるのでしょうか。
財産隠しをするとどうなる?
財産分与を避けるために、財産を隠したり、離婚の直前になって高額な買い物をしたりするケースは少なくありません。
へそくりとして貯めていたタンス預金や、配偶者の知らない口座で管理している預貯金、自分名義でこっそり購入した不動産など、申告しなければ相手にバレないのではないか?と考える方も多いでしょう。
財産分与の際に「財産隠し」とされるのは、主に以下のような行為です。
・銀行口座や株式などを配偶者に申告せず、財産一覧に含めない
・親族名義や法人名義に変更し隠匿する
・配偶者に内緒で不動産を購入し、自分名義にしておく
・預金や資産を引き出し「存在しない」「使ってしまった」などと虚偽説明
これらは、財産分与を不当に逃れる目的での行為であり、極めて悪質とされます。
調査嘱託や弁護士会照会で発覚する可能性
離婚時の財産分与では、お互いの財産状況を把握するために財産開示請求を行うことができます。
当人同士の話し合いでは、財産開示請求があってもそれを拒否することは可能ですが、「調査嘱託」や「弁護士会照会」を利用された場合、本人の許諾がなくても情報が開示される可能性があります。
①調査嘱託
離婚調停や裁判において、裁判所を通じて金融機関等に財産状況を照会する「調査嘱託」の方法があります。調査嘱託を利用されれば本人の許諾に関係なく財産状況が相手に開示されることもあります。
②弁護士会照会
相手方が弁護士を通じて銀行や証券会社に財産の開示を求める「弁護士会照会(23条照会)」があります。
弁護士会照会とは、弁護士が弁護士法第23条に基づいて行う情報照会制度で、弁護士が依頼を受けた事件(民事・刑事・家事など)の解決に必要な情報を、一定の機関や団体に対して弁護士会を通じて照会・開示請求できる仕組みです。
これにより、名義を隠していた口座や不動産の保有が判明するケースは少なくありません。
仮に一時的に財産を別口座に移しごまかしたとしても、その履歴をたどられてしまうこともあるため、短絡的な隠匿行為はリスクが大きいと言えます。
財産隠しが発覚した場合の法的責任とデメリット
財産隠しが明るみに出た場合、隠されていた財産を含めたうえで再計算されます。
再計算のためさらに時間を要することになりますし、相手方との円滑な話し合いに支障をきたすおそれがあります。
円満な離婚を望むのであれば、隠し財産や不正な浪費行為は避けるべきでしょう。
4.共働き夫婦の場合、財産分与をしなくてもいいのか?
共働きの夫婦でお互いに離婚後の生活を安定的に送ることができる収入がある場合、財産分与はしなくてもよいのではないか?と思われる方もいらっしゃるでしょう。
結論からお伝えすると、財産分与の基本的な考え方は共働きであっても変わりませんので、原則として2分の1ずつで夫婦の共有財産を折半します。
話し合いの結果、双方が合意できれば、2分の1以外の割合で自由に財産を分けることも、財産分与を行わないことも可能です。
それぞれの収入を自分の口座で管理している場合
夫婦がそれぞれの収入を個別の口座で管理しているような、いわゆる“財布は別”という状態でも、婚姻後に形成した財産蓄積であれば、それが特有財産に該当しない限り財産分与の対象になります。
共有財産と特有財産をどう区分するかは離婚時に重要な争点となるため、注意が必要です。
5.離婚をしないことで財産分与を回避する選択肢はある?
協議離婚や調停離婚においては、双方が離婚に合意しなければ離婚自体を回避することは可能です。
ただ、財産分与をしたくないことを理由に離婚をしないのは、本末転倒であり、感情面や生活面でさらに大きな負担につながるおそれがあります。
6.財産分与の減額交渉ができる場合とは?
相手から財産分与請求がなされた場合、法的には原則として拒否できません。
なるべく財産分与をしたくない場合は、減額や別の形での交渉を検討する必要があります。
協議が難航する場合には、弁護士など専門家のサポートを得るのも一つの手段と言えるでしょう。
慰謝料や養育費との調整や交渉を検討する
財産分与の代わりに、ほかの離婚条件(例えば、「養育費の金額を養育費算定表で示される相場額よりも多く支払う」などで合意する)で支払い金額の調整を行う方法などを検討できる場合があります。
離婚の原因が相手の不倫やDVなど有責行為によるものであれば、慰謝料を請求する権利が発生する場合があります。
そこで、慰謝料を請求しない代わりに財産分与も求めないことを合意するなど、ほかの離婚事件との間で調整する方法も考えられます。
ただし、個別の事情と交渉経過次第ですので、弁護士に相談するなど慎重に検討することが大切です。慰謝料が請求できる条件などについては、こちらのコラムで詳しく解説しています。
分配割合の修正を求める主張をする
配偶者の一方が経営者や、特殊な能力を必要とする職業(医師など)であった場合には、財産分与の割合が修正されることがあります。
これは、一方配偶者の収入が、その個人が兼ね備えた能力によるものであるところが大きいと判断されるためです。
また、経営者である場合に、法人名義の財産を「夫婦の共有財産」とすることは原則としてありませんが、個人事業主の場合や、夫婦で経営に携わっていたなど個別の事情により、法人名義の財産についても財産分与の対象となることがあります。
もっとも、原則として2分の1を分与することは上記のとおりです。
このような主張をするには客観的資料に基づく立証が必要であることに注意しましょう。
なお、相手方の浪費を指摘して分与割合を下げる主張をすることも考えられますが、このような主張が認められるのは極めて限定的な事例になります。
7.財産分与問題を弁護士への相談するメリット

離婚時の財産分与は、単に共有財産を半分に分けるだけではありません。
特有財産の主張や、将来の生活設計、子どもの養育費や慰謝料請求との兼ね合いなど、複雑な要素が絡み合い財産分与の割合が修正されることがあります。
法的な手続きや請求期限、書類作成のポイントなどを知らないまま独断で判断すると、後々後悔する結果になるかもしれません。
離婚時の財産分与でお悩みの場合には、早い段階から専門家である弁護士に相談することが重要です。
財産分与を含めた離婚条件の交渉を代理人として行い、法的根拠に基づいた客観的なアドバイスをすることで、スムーズな問題解決を目指すことができます。
特に財産規模が大きい場合やトラブルが深刻化している場合には、早めの相談を検討しましょう。
一新総合法律事務所の離婚チーム弁護士
一新総合法律事務所では、離婚問題に注力する離婚チーム所属の弁護士が対応いたします。
ひとりひとりのお悩みに寄り添いながら丁寧に聞き取りをし、あなたの状況に応じた適切なアドバイスを行います。
自分自身の人生設計と相手やご家族の将来を踏まえた話し合いを大切にし、一歩ずつ確実に進めていきましょう。
離婚に関するご相談は1回5,000円/45分、不貞に関する慰謝料請求当のお悩みは初回相談無料で承っております。
ひとりで悩まずにまずはお気軽にご相談ください。